2.3. 結果
図2.2に実験結果を示す。3.3 sec間の画像を重ね合わせたものであり、可視化粒子の流線が見られる。可視化粒子の慣性を無視すれば、流線は実際の液体の流れと一致する。照明の不均一を解消するため、長時間の平均をバックグランドと仮定してそこからの差をとるという方法を用いた[5]。BZ反応溶液相、オレイン酸相共に、界面近くで化学波のウェーブフロントに向かって引き込むような流れが見られる。また、化学波の前方と後方では、流れの速さが全く異なり、前方での流れの方が、後方よりもずっと大きい。
対照実験として、オレイン酸にヨウ素(I2)を溶解したものを用いて、同様の実験を行った。ヨウ素は界面からBZ反応溶液へと拡散する。ヨウ素は水に溶けてイオンとなったときに、BZ反応に対して、抑制因子として働く。そのため、BZ反応波は界面まで到達しない。同様に3.3 sec間の画像を重ね合わせたのが図2.3である。このとき、流れはほとんど観測されなかった。
2.4. 考察・シミュレーション
この対流現象は、鉄錯体の価数による界面張力の違いに起因するMarangoni効果であると思われる。そこで、実験結果を説明するために、流体力学の基礎方程式であるNavier-Stokes方程式を用いた。流れは音速に比べて十分にゆっくりであるので非圧縮性(
ρは流体の密度、
過去に界面張力はフェリインの濃度にほぼ比例するという報告があり、(図2.4参照)もっともな仮定である。なお、以下では簡単のため、2次元で考え、界面に平行な方向にx軸を界面に垂直な方向にy軸をとることとする。
ところで、BZ反応では、反応波のモデルとして、反応拡散方程式、及び2次元オレゴネーターがよく用いられる。U を活性因子の濃度、V を抑制因子の濃度とすれば、一般的に次式のように表される[6]。
具体的には、活性因子は亜臭素酸(HBrO2)、抑制因子はフェロイン([Fe(phen)3]3+)に対応する。また、f、ε、qはそれぞれ、閾値、興奮性、無次元化した速度定数を表すパラメータである。今回、溶液の流れを考えているため、オレゴネーターに移流項を付け加えるべきであり、次式のようになる。
また、V はフェリイン濃度であるため、界面張力の式に入れることができ、界面張力の式は、次のように書き直すことができる。
以上により、Navier-Stokes方程式(2成分)(2.1)、界面張力の式(2.5)、反応拡散方程式+2変数オレゴネーター(2.3)の5つの方程式が得られた。未知数は速度
今回は、簡単のため、(2.3)式の移流項を抜いた形(2.4)式を用いて数値計算を行った。こうすることによって、オレゴネーターを独立に解くことができ、界面張力を求めてから、流体の計算をすることができる。境界条件は、界面で界面に平行な速度成分しか持たないとした。その他の境界条件は、十分遠い壁で速度0とした。(2.4)式は、x軸方向のみの1次元で解いた。
以上の数値計算の結果を図2.5に示す。反応波の前方で強い引き込みの流れが観測される。前方と後方の流速の比は、シミュレーションでは(前方)/(後方)=1.4になる。一方、実験結果から測定すると、比は約5.0である。比の値は異なるが、定性的に一致した結果が得られた。
過去に、BZ反応に起因する対流現象の研究は行われてきた。だが、重力の影響であるとしたもの[3]や、濃度差によるMarangoni対流の平衡論から説明したもの[4]であり、ダイナミクスを考えたものはなかった。今回、重力加速度と垂直な面内で実験を行っており、重力の影響でないことを明らかにした。また、化学波の位置は時間的に変化するため、平衡論で取り扱えるかどうかは疑問である。実際、化学波の速度と対流の速度は、実験結果から測定すると、前方での流れの速度よりは遅く、後方での流れの速度よりは速いという結果が出た。今回、Marangoni効果をあらわに方程式に組み込まずに数値計算し、その結果、対流の発生を説明できたため、Marangoni対流に関しては平衡に近い状態になっていると考えられる。
今回は、反応拡散方程式+オレゴネーターの式(2.3)の移流項
2.5. 結論
BZ反応溶液とオレイン酸の界面において、化学波のフロントに引き込むような対流現象を実験的に観測した。また、抑制因子を拡散させることにより界面に化学波が到達しない状態では、対流が発生しないことを確認しており、対流現象は化学波が界面に到達することによってはじめて発生することを示した。また、基礎方程式であるNavierStokes方程式に界面張力を取り入れて数値計算を行ったところ、化学波の前方で強い流れが発生するなど、実験と定性的に一致する結果が得られ、対流が発生するダイナミクスを説明することができた。
第3章 BZ反応液滴の自発的運動
3.1. はじめに
非平衡開放系においては、リミットサイクルを用いることによってエネルギーを仕事に変換することができる。このとき、平衡系でのCarnotサイクルのように高温熱源と低温熱源を用いる必要がなく、熱拡散が非常に効いてくる小さなスケールにおいてもエネルギーを仕事に変換することができる。生物細胞の分子機械もこのような非平衡開放系の特徴を利用して、化学エネルギーを仕事に変換することにより働いていると考えられる[7]。
しかしながら、現在まで、実験系として等温系で化学エネルギーを仕事に変換する系はほとんど見つかっていなかった。わずかに、油虫[8][9]、水に浮かべた樟脳[10][11][12]、水銀の心臓[13]、水銀のアタック[14]、ゲル系BZ反応でのゲル振動[15][16]などが知られているだけである。今回は、非平衡開放系のモデルとしてよく使われるBZ反応で化学-機械エネルギー変換を行う実験系を構築することができた。BZ反応を用いたゲル系では、ゲルの振動が報告されているが、約1 %しかサイズが変化していない[15]。今回の実験では、サイズの約30 %の並進運動を取り出すことができた。その運動のメカニズムについて、第2章で用いたのと同じ方程式を用いて解析を試みる。
3.2. 実験装置・方法
シャーレにオレイン酸を厚さが約3 mmになるように注ぎ、その上にマイクロピペッターを用いてBZ反応溶液を1.0 ml静かに滴下した。デジタルビデオカメラに拡大レンズを取り付けたもので、上から撮影し、その映像をPCで解析した。(図3.1参照)なお、BZ反応溶液の組成は下に示す。(第2章のものと比べて硫酸濃度のみを大きくし、自発的に化学波が発生しやすいようにした。第2章のときと同様に、界面張力効果を大きくするため、フェロイン濃度は大きくしてある。)
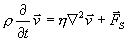 (3.5)
(3.5)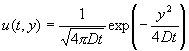 (3.8)
(3.8)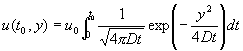 (3.9)
(3.9)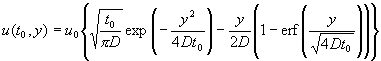 (3.10)
(3.10)